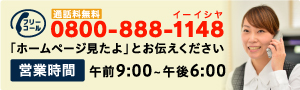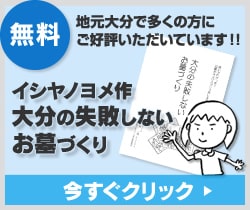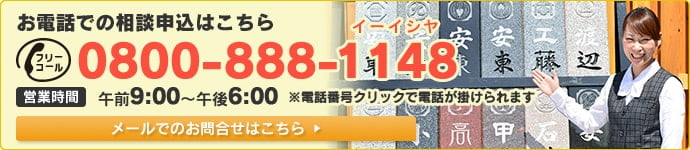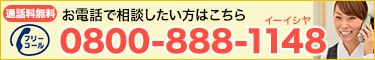弥生時代のお墓はどんなお墓?
更新日2023年12月05日
こんにちは。
「イシヤノヨメ」こと安東一美です。
前回は縄文時代のお墓についてお話ししましたが、今回は弥生時代のお墓です。
弥生時代のお墓
弥生時代のお墓といえば、佐賀県の「吉野ヶ里遺跡」が有名です。

この集落は約30ヘクタール(500メートル×600メートルが30ヘクタール)もあり、
もしかすると、「邪馬台国」だったのではないかと言われるほどです。

さて、弥生時代のお墓も先日の縄文時代のお墓と同様、集落の北には出入口と道があり、お墓の横から列状の埋葬地を通って居住区へと続いています。
「死者を大切にし、生きている人と共に暮らした」形跡が認められるそうです。
そして、縄文時代と違うのは「副葬品」がたくさん出土しているという点です。
現代でも少し前までは、棺桶に六文銭を入れ、亡くなった人に手甲(てっこう)・脚絆(きゃはん)・杖・わらじを持たせて旅装束にしていたそうですが、亡くなった人が「冥途の旅」をすると信じていたと言われています。
副葬品がたくさん出土したのは、弥生人にもそういった気持ちがあり、一緒に埋葬したのではないかと言われています。

さて、北九州一帯からは特有の埋葬法である「甕棺(かめかん)」が2,000基以上も出土しており、小児用の甕棺も見つかっています。
甕棺のルーツは中国大陸にあり、「二次葬」とか「複葬」と言われ、いったんお骨にして、改めて甕棺にご納骨したそうです。
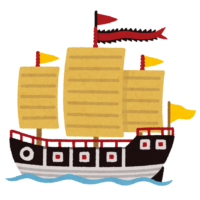
こうしてお墓のルーツを探ると、やはり一生懸命生きてきた人に今一番の出来る供養を。と思う気持ちは変わらないのだと思うのでした。