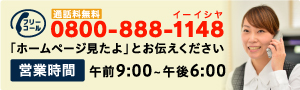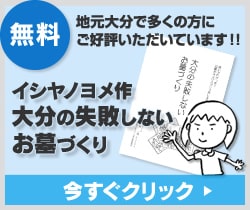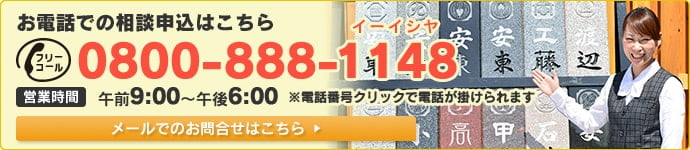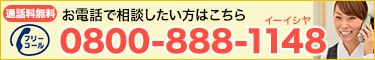世界の葬法の違いについて
更新日2023年08月02日
こんにちは。
「イシヤノヨメ」こと安東一美です。
毎日暑いですね。
もうすぐお盆。
猛暑ですので、お墓のお掃除などは涼しい時間にチャレンジしてください。
さて、今日は世界の葬法の違いを少しご紹介してみたいと思います。
世界の葬法の違い
インドのヒンドゥー教
インドのヒンドゥー教では、幼児と出家者は土葬を行い、
それ以外の方は火葬を行います。
火葬を行うと「プレータ」と呼ばれる霊魂は頭蓋骨から出てあの世へと
旅立ち、その10日後に新しい体を得るため生まれ変わるそうです。
お骨は霊魂の抜け殻とされ、聖なる河ガンジスへと流されるそうです。

インドのイスラム教
同じインドでもイスラム教になると
「火葬は神を冒涜(ぼうとく)する」という考え方から土葬にします。
霊魂は埋葬した翌日に肉体から出ると信じられ、お墓参りの習慣もありません。
チベットでは
亡骸はハゲワシが食べやすいように細かく切り砕きます。
亡骸を食べられることで死者の霊を早く天界に運んでもらうと
信じている「鳥葬(ちょうそう)」の国です。
しかし、全て鳥葬ではなく、土葬や火葬、水葬、ミイラもあるようです。

キリスト教のカソリック
火葬して遺体が亡くなることを嫌います。
「最後の審判」の日に遺体がないと天国へいけないと信じられています。
また、火葬は魔女や異端者の拷問刑である「火あぶり」とみなされます。
教会や聖者の像に近いところへ埋葬されることが多いようです。
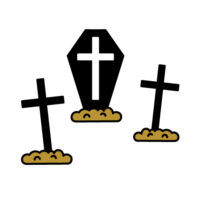
中国・朝鮮半島
「儒教」や「風水思想」、「道教」の考えが強く残っているため、土葬が多いです。
「両親からもらった身体を傷つけないことが孝(こう)の始まり」と儒教の経典にあり、
遺体を焼くなどもってのほかで、遺体を保存できる土葬が伝統的な葬法となっています。
さて、いかがだったでしょうか。
意外と「火葬」する国が少ないのに驚きます。
日本も昭和40年代くらいまで土葬が行われていたようです。
文化や宗教による違いに驚かされますね。
ではまた!!