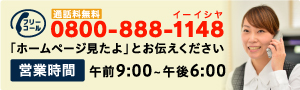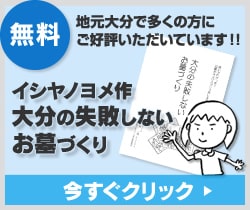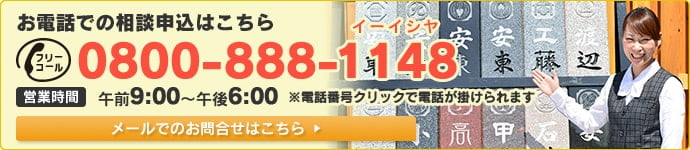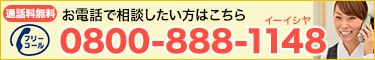お墓の各部にも名称や意味があるんです。
更新日2024年07月15日
こんにちは。安東石材店の溝江です。
本店の総務部では、墓石に関する知識を深めようと様々な事を調べています。
その中で、今回はお墓の各部について調べてたことをご紹介します。
昔からあるお墓ですが、お墓の各部にはそれぞれ名称や意味があることをご存じですか?
各部の名称と意味

竿石
- ・竿石(さおいし)とは、お根性が入るお墓のもっとも中心となる部位のこと
- ・「軸石」や「仏石」などとも呼ばれ、正面に「〇〇家乃墓」などと彫刻
- ・この竿石にお性根が入るとされているので、お墓の中でも最も大切な場所
- □お墓におけるお性根は、竿石に込められています。
- 「お根性」とは「魂」みたいなもので、仏さまの魂や、故人や先祖の魂はこの竿石に込められています。
- お墓参りの際はぜひこの竿石に向かって手を合わせ、語りかけてみてください。
上蓮花
・上蓮華(うえれんげ)とは、竿石と上台の間に挟み込む飾り石で、竿石を乗せるための蓮華彫刻が施された部材
□泥池に咲く蓮の花は、仏教の中でも特に大切にされてきた花です。お墓においても、本尊である竿石を蓮の花の上に載せることは大変な功徳とされています。ただし、費用がどうしもてかかってしまうので、蓮華のないお墓の方が多いのが実情です。
下蓮花
・下蓮華(したれんげ)とは、上蓮華と対となるもの
□上蓮華のみと、上下蓮華と選ぶことができます。下蓮華は上台の天面を加工して作ります。
上台
・上台(うわだい)とは、台石の中で一番上部に据えられる石のこと
□上台の天面を加工することで、さまざまなデザインができます。
上蓮華に対応してなされる”下蓮華”では蓮の花ビラ状に加工します。
その他、亀のおなかのようになめらかなこう配をつけた”亀腹加工”や、傾斜を付けた水が流れるような”水垂加工”などがあります。
中台
・中台(なかだい)とは、台石の中で真ん中に据えられる石のこと
□中台を「下台」と呼ぶ地域もあります。
芝台
・芝台とは、台石の中で一番下部に据えられる石のこと
□この芝台を「下台」と呼ぶ地域もあります。
また、1つの石で作るものに対し、4つの石を組み合わせて作る場合は「四つ石」などとも呼ばれます。
水鉢
・水鉢(みずばち)とは、水を供えておくための石
・天面にくぼみ(「水溜」とも呼ばれる)を作っておき、お供えの水や雨水が常に溜まるようにしておく
□死者がのどの渇きに苦しみために作られたものだと思われます。
この水溜は、江戸時代などの古いお墓でも、台石の天面に作られているものもあります。
また、地域によってはこの水鉢がカロート(納骨室)の蓋としての役目も果たしています。
ずっと水を溜めておくために汚れやすいので、専用のステンレス製の浅皿も販売されています。

花立
・花立(はなたて)とは、花を供えるための石で、左右一対で置かれるのが一般的
□花立の穴の中も水が溜まりやすいため、最近では横穴を開けて、水が外に流れ出るよう工夫されています。

香炉
・香炉(こうろ)とは、お線香を供えるための石
□香炉にもさまざまな種類があり、丸型の香炉、屋根付き香炉などがあります。
また、宗派によってはお線香を寝かすので、寝かせてお供えができるステンレスの皿も販売されています。


お墓は昔から身近にあるものですが、あって当たり前と思っていた各部の名称や意味、お墓の背後にある歴史を知ることで、故人やその家族に対する思いや感謝の気持ちがより深まるかもしれません。お墓参りがより意味のあるものに感じられるかもしれませんね。