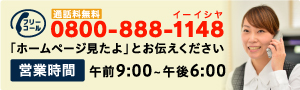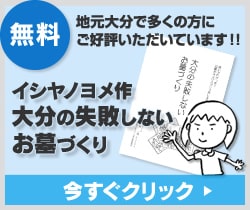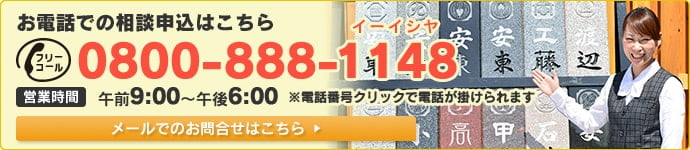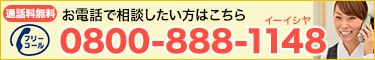家紋って…何だろう?!
更新日2025年06月08日
こんにちは。
安東石材店の溝江です。
家紋といえば、着物に刺繍されているものや、お店の暖簾、お墓に彫刻されているものなど、日常生活の中ではあまり目にする機会のないものです。しかし、これらの家紋にはどのような意味が込められているのでしょうか?また、どのような種類が存在しているのでしょうか?

今回は、その「家紋」についての謎や背景について、詳しくご説明いたします。
家紋(かもん)とは?
家紋は、家族や一族を象徴する模様や紋章のことです。家族ごとに決まったデザインがあり、それを使うことで「この家族のものだよ」と示す役割を果たしてきました。
家紋の起源はいつ?
家紋の歴史はとても古く、平安時代(約1,000年前)にさかのぼります。当時の貴族や武士たちが、自分たちの家や一族を区別するために紋章を使い始めたのが始まりです。

なぜ家紋をつけたの?
戦国時代や戦国時代の頃には、戦いの中で自分たちの旗や鎧に家紋をつけて、味方や敵を見分けやすくしました。また、家族の誇りやアイデンティティを示すためにも使われました。
江戸時代に入ってからは?
平和な時代になった江戸時代には、家紋はより多くの人々に広まり、着物や家の暖簾(のれん)、墓石などさまざまな場所に使われるようになりました。
これにより、家族や一族のつながりや誇りを表す大切なシンボルとなりました。
今の時代はどう使われているの?
現代でも、家紋は伝統や家族の歴史を大切にするために使われています。結婚式やお墓、伝統的な行事などで見かけることがあります。

日本五大紋教えます!
木瓜紋(もっこう)

荒地や畑に群生する繁殖力の強い雑草の一種で、子孫繁栄を意味するとも云われています。
文様としては古く唐時代に用いられ、日本へ伝来しました。「木瓜」と記すので瓜の切り口を連想しますが、本当は地上の鳥の巣を表現したものとされています。
鷹の羽紋(たかのは)

古来より武家にはとても人気のある紋だったようです。江戸時代には、実に120家の大名旗本が、鷹の羽を用いていたそうです。
桐紋(きり)

室町幕府では小判などの貨幣に刻印され、これ以来皇室や室町幕府や豊臣政権などが用いており、現在では日本国政府の紋章として用いられています。
藤紋(ふじ)

ヤマフジのぶら下がって咲く花と葉を「藤の丸」として図案化したもので、元来は「下り藤」です。
片喰紋(かたばみ)

片喰・酢漿草は、カタバミ科カタバミ属の多年草で、繁殖力が強く、一度根付くと絶やすことが困難であることが、「(家が)絶えない」に通じることから、武家の間では、家運隆盛・子孫繁栄の縁起担ぎとして家紋の図案として用いられた。
ぜひこの機会に、ご自身の家の家紋も探してみてくださいね。意外なルーツや歴史に出会えるかもしれません!