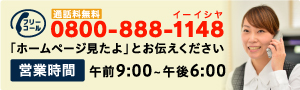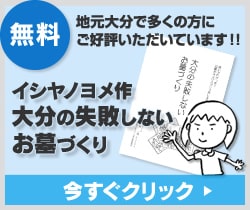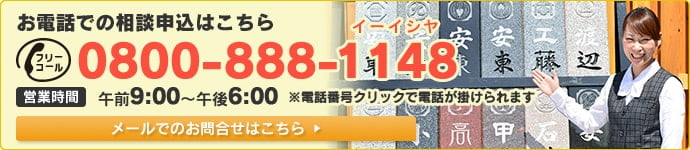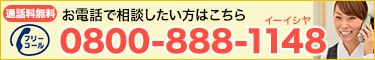仏教の修行期間「雨安居」(うあんご)知っていますか?
更新日2025年06月08日
こんにちは。安東石材店の溝江です。
もうすぐ梅雨が来ますね☔️この梅雨の時期に「雨安居」(うあんご)という仏教の修行期間があるのをご存じですか?
今回は「雨安居」(うあんご)についてお話しします。

雨安居(うあんご)とは?
「雨安居」は、インドの雨季に僧侶が外出を控え、一定期間一カ所に留まって修行に専念することを指します。
サンスクリット語では「ヴァルシャ(Varṣa)」と言い、直訳すると「雨」または「雨季の修行期」という意味です。
自然保護の精神(アヒンサー:不殺生)
雨季には地面に多くの虫や小動物が出てきます。外を歩くことで、無意識に命を踏み殺してしまう可能性があるため、それを避ける意味がありました。
修行に集中できる環境
移動せず、一定期間同じ場所に留まることで、瞑想や教えの学びに集中できる。

仏教教団の安定と団結
僧たちが一堂に集まり、教えを共有し、共に修行することで、教団内の結束も高まります。
期間
インドの雨季にあたる 旧暦の4月15日(現代の6~7月)から3か月間
日本では正式な制度としては行われていませんが、思想的には伝わっています。
雨安居と日本仏教
日本の仏教では、正式な雨安居の制度はないものの、「夏安居(げあんご)」や「結夏(けつげ)」と呼ばれる修行期間があり、禅宗(特に曹洞宗・臨済宗)で見られます。
禅寺では、夏の3か月間に集中して坐禅を行う「安居」が続いているところもあります。
現代的な意義
現代ではこの習慣を通じて、「じっと留まり、自分と向き合う大切さ」「自然や命を大事にする心」が見直されています。
雨音や静けさの中で、心を落ち着かせる時間をもつことが「現代の雨安居」とも言えるかもしれません。

雨季に自然の命を傷つけないよう寺にこもって修行する伝統があって、梅雨の時期にぴったりの精神だなと感じます。雨音の中で心を整えるひとときを、現代の私たちも大切にしたいですね。